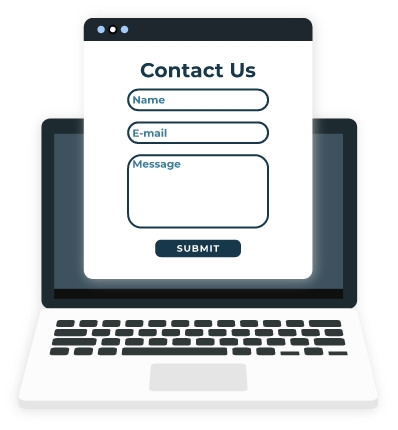医療・福祉業
RPAで旧電子カルテの移行作業を自動化。医療業界のDX化をRPAで実現
- 電子カルテ
- BtoC

在宅医療の支援や、高齢者・がん・難病・障害者医療の専門家として診療をおこなう医療法人社団創福会 ふくろうクリニック等々力 黒谷様にRPA導入前の課題、RPA活用法や成果・効果についてお話を伺いました。
課題
- クラウド型の電子カルテへの移行により、約8万件にも及ぶ膨大な患者データの移行作業が必要に
- 業務の属人化においてトラブル発生の懸念があった
- 医療のDX(デジタルトランスフォーメーション)化を実現させたかった
効果
- 従業員のリソースを使わずに、費用を大幅に抑えてデータ移行が可能に
- 専任の担当者を配置することなく、費用面・リソース面の両方で抑えることができた
旧カルテシステムからクラウド型の電子カルテシステムへ8万件移行する必要があった
医療法人社団 創福会は2拠点でクリニックを運営している医療法人です。病院に通うことが難しい方を対象とした訪問診療が主な事業ですが、一般外来もございます。法人全体では訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所と、全部で4つの施設を運営しています。
私自身は医療の専門職ではなく、医療以外の法人組織として必要な業務を統括しております。具体的に経営管理やWEBマーケティングを用いた営業活動や各部署の業務改善の施策立案・実行だけでなく、人事採用部門といった総務としての役割も担っております。また、IT関連の設定や導入、フォローアップにも携わっております。
当院の旧電子カルテがサーバー型でWindows7対応だったため、クラウド型の電子カルテへの移行が必須課題となっていました。現在当院には4,000人強の患者様がいますが、一人当たり20件程度の診療録があり、4,000人×20件=8万件と膨大な量のデータの移行が必要だったのですね。これはとても人の手では間に合わない作業であり、ITツールを使用して行わなければならないと感じていました。
また、属人的な業務全般に言えることですが、担当者が退職し、知見のある人がいなくなったらトラブルが発生するのではないかと以前から懸念していたのです。そういった背景を踏まえて、医療のDX(デジタルトランスフォーメーション)化を目指そうという想いで展示会に足を運んでいたところ、スターティアレイズさんのRoboTANGOに出会いました。
自社で活用できるツールがないか情報収集しに、1年に1~2回ほど展示会に行っています。
今回も電子カルテの移行業務で役立つツールはないか情報収集するために参加していました。
2020年に別の展示会やセミナーに参加し、RPAの説明を受けたことはありましたが、当時は実運用のイメージがわかずに導入には至らなかったのです。しかし、2021年の秋に訪れたときには商品や価格帯が2020年よりもはるかに広がっていてRPAの進歩を感じましたね。
また、アウトソーシングや派遣スタッフの雇用なども検討し、色々な選択肢がある中で最終的にRPAの導入に至りました。
リーズナブルな価格と営業担当の対応がRPA導入の決め手
 シナリオ作成をわかりやすくレクチャーしてくれた営業担当の対応
シナリオ作成をわかりやすくレクチャーしてくれた営業担当の対応 リーズナブルな価格
リーズナブルな価格 人並程度のリテラシーでも理解できる操作性
人並程度のリテラシーでも理解できる操作性
私たちはRPAを導入する課題と目的が明確でしたので、一緒にシナリオ作成をわかりやすくレクチャーしてくれたスターティアレイズさんにお願いしたいと思いました。月額費用を抑えられて、比較的リーズナブルなところも決め手のひとつです。
RoboTANGOに関しては操作がわかりにくいということがほとんどないですし、どこに何があるのかも非常にわかりやすく、助かっています。私ともう一人の職員が運用に携わっているのですが、RPAロボットに関するリテラシーは二人とも人並み程度です。しかし、RoboTANGOは人並み程度のリテラシーでも理解できる仕組みで、使いやすいと感じています。
また、導入前から今に至るまでの、充実したサポート体制にも助けられています。トライアル期間も営業担当の方から具体的に教えていただくことができたので、非常に有意義なものとなりました。
日中だけで200件のデータ移行の自動化を実施。コスト面・リソース面両方で抑えられた
前例のない業務ですので比較が難しいところですが、この業務専属の担当者を配置しても1年単位くらいで作業してやっと完了する程度のボリュームなので、費用面・リソース面の両方で抑えられたと感じています。現在は平均で1日10人分程度(10人×20件=200件)のデータ移行ができていますね。
基本的には平日の日中帯に院内で動かしています。
旧電子カルテがサーバー型のため、システムが入っている端末でRPAを動かす必要があり、対象のPC1台で稼働させています。古い端末という事もありシステム側のエラーが発生して止まってしまうこともありますが、それは仕方ないかなと感じています。
まだまだシナリオのブラッシュアップは必要なので、改善していきながら処理を進めていきたいです。
今後は属人化した業務の自動化にも取り組みたい
そうですね。半年以内にはあらゆる部署の業務改善や課題解決に活用していくことを目標にしています。当院は部署ごとの縦割りや属人的に近い業務も多く、業務の問題点や担当者を見える化できていない事情もあるため、そこも解決していかなければなりません。
RPAを活用するうえで業務の洗い出しをした際に、「本当にこの業務が必要なのか」という議論が出たり、無駄な業務をなくすということもしていこうと考えています。
業務を見える化することで、社員それぞれの業務内容や、残業の偏りなどの発見にもつながると思うので、そういった課題解決もしていきたいです。
また、社内申請においては紙運用をしていることが非常に多いため、そういったこともOCRとRPAを組み合わせて活用したりして、自動化したいと考えています。
現場のスタッフにRPAやOCRについての説明をしてもなかなか理解されず、説得するのに苦戦しました。
効率化・簡易化できるとなった際に、元々の担当者は自分の仕事がなくなったと感じてしまい、反発が多少ありました。空いた時間はさらに深い業務に充てることができることを理解してもらい、ツールについて説得していくことが必要だと思います。
誰もが使えるRPAになるよう期待
レコーディング機能ですべて完結できるようなかたちまで落とし込めたらより簡易的な操作で済むようになり、どの職員も扱えるようになるのではないかと期待しております。
汎用性のあるシナリオがテンプレート化されていれば、もっと業務が効率化されるのではないかと思いますね。システムを教える側も教えられる側も、レクチャーの負担がかなり軽減されるのではないでしょうか。今後の医療のDX化を促進するためにも、RoboTANGOのさらなる進化に期待をしています。
医療法人社団創福会 ふくろうクリニック等々力
https://www.296296.jp/
認知症、がん、神経難病の専門医療に特化した医療クリニック
100名
RPAツール「RoboTANGO」
総務部門
無