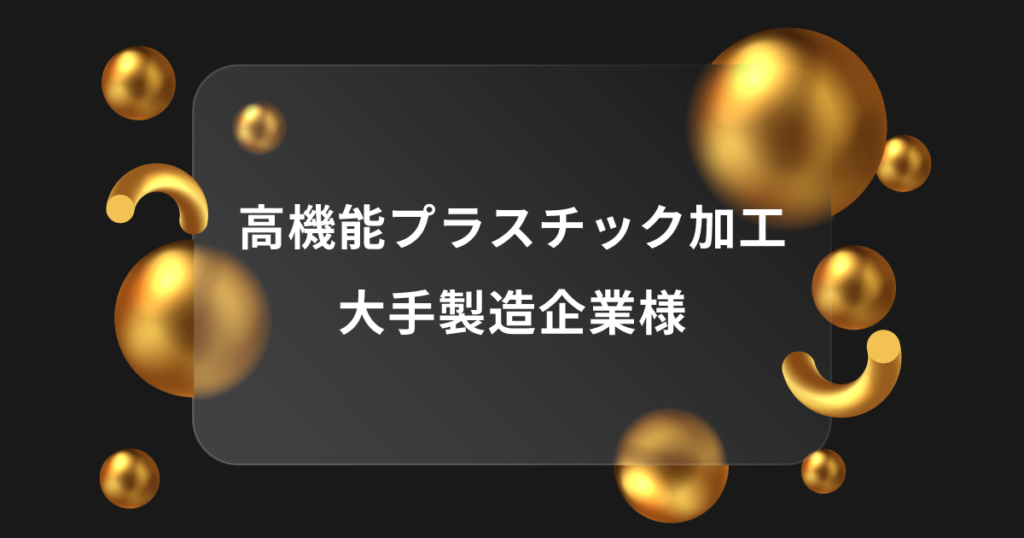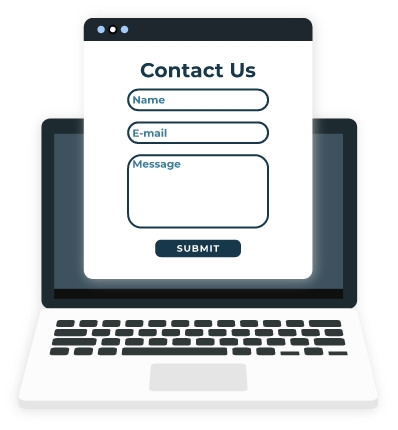製造業
RPA導入で製造業におけるMRP処理やマクロ、受注データ取り込みの操作を自動化し、月間60時間以上の工数削減に成功
- 基幹システム
- Excel/CSV
- VBA マクロ

建設用機械、産業用機械の金属部品の加工を行う富士精機株式会社の代表取締役専務 川島様とIT企画室 統括SE新谷様、田子様にRPA導入前の課題をはじめ、活用方法やRPA導入後の成果・効果についてお話を伺いました。
課題
- 所要量計算(MRP)・工程計画修正など基幹システムまわりの処理に毎朝2時間以上かかっており、IT担当者の工数が大きな負担となっていた
- 排他制御や処理遅延により、現場や事務所での入力作業・生産計画作成が滞り、工場全体の生産性が低下していた
- 毎朝の定型処理を人手で実行しており、タイムリーなデータ提供や早朝稼働が難しかった
効果
- 所要量計算(MRP)、工程計画修正、受注データ取り込みなどの自動化により、月間約60時間の工数削減を実現
- 出社時には全ての処理が完了している状態となり、業務の滞留が解消・現場の生産性が向上
- 手作業・ヒューマンエラー・引き継ぎ作業がなくなり、安定稼働とリアルタイムな情報共有が可能になった
高い精密研削加工技術と若い力で成長を続ける富士精機株式会社

川島様:富士精機株式会社は、1957年の創業以来、精密研削加工をはじめとする研削加工を主体とした部品加工を手がけています。建設・産業用機械向けの金属部品加工を中心に、材料調達から切削・研削・熱処理・表面処理といった工程までを一貫して対応できる体制を整えているのが特長です。高精度な製品加工を支えるのは、旋盤と研削盤を中心とした生産設備で、なかでも精密研削加工は全体の7割を占めており、幾何公差や面粗さなどμ単位の高い精度が求められる製品も得意としています。さらに、8割以上の製品に熱処理工程を通しており、高硬度材の加工にも強みがあります。

弊社では、2012年に36名だった社員数が現在76名まで増え、女性比率は25%を超えており、さらに10代〜30代が全体の50%、40代まで含めると75%を占め、若い世代を中心とした活気ある組織が強みです。IT企画室や品質保証部、生産技術部など専門部署を設け、ニーズに応える柔軟な提案を行っています。また、「営業ができる工場」を目指しながら、5S活動の徹底や制服・食堂の刷新、キッチンカーの導入など、働きやすい環境づくりにも注力しています。ブッシュをはじめとした建設機械分野を主軸に、近年は船舶・環境機械分野へと事業領域を広げ、多品種少量生産にも対応できる体制で、今後も成長と社会貢献を目指しています。
工場全体の生産性低下とIT部門の負担増がRPA検討のきっかけに
新谷様:当社は、約15年前にオンプレ型のクライアントサーバー・モデルの生産管理用基幹システムを導入しました。導入当初は規模も大きくなく、特に問題なく運用できていましたが、業容の拡大に伴い徐々に課題が顕在化してきました。このシステムはベンダーのパッケージソフトであるため、部品メーカーである当社の業務に一部適合しない部分が出てきたのです。
主な課題は2点あります。まず一つ目は、基幹システムの「所要量計算(MRP)」画面で毎日作成する工程計画が、当社の想定と乖離しており、納期遅延のリスクがあったことです。二つ目は、データベースの排他制御の関係で、一部の更新系画面が同時に1画面しか開けない点です。
このうち工程計画の乖離については、当社が入力しているマスターデータの精度が十分でないことも一因でした。そこで、基幹システムを補完して工程計画を作成する「工程計画修正マクロ」を社内で開発。さらに、基幹システムのデータベースや計画ファイルをもとに管理データを作成するマクロも複数開発しました。しかしその結果、更新画面の排他制御を回避しながら毎日処理を実行する作業や、マクロ群の実行・管理データの提供といった業務が毎日2時間ほどかかってしまっており、IT担当者の大きな負担となっていきました。タイムリーなデータ提供のためにも、この負担を軽減することが喫緊の課題となっていました。
さらに、排他制御にはもう一つ問題がありました。システム利用者の増加によって更新画面で待ち時間が発生しやすくなり、加工現場での実績入力などトランザクション処理にも遅れが生じるようになったのです。特に、毎朝実行する「所要量計算(MRP)」は処理時間が長く、他の画面操作にも影響を及ぼしていました。こうした状況は事務所や加工現場を問わず工場全体の生産性の低下につながっており、早急な解決が求められていました。そのため、夜間や早朝の無人時間帯に自動で作業を実行できる仕組みの検討を始めました。
RPA導入の決め手は、中小企業での導入実績や操作性、手厚いサポート体制
RoboTANGOの導入を決めた大きな理由は以下の5点です。
 中小企業での導入実績が多いこと
中小企業での導入実績が多いこと トライアル期間があること(トライアル期間中に実用化の目処を立てられる)
トライアル期間があること(トライアル期間中に実用化の目処を立てられる) 画面の操作登録が容易であること
画面の操作登録が容易であること Excel VBAマクロとの連携が可能であること
Excel VBAマクロとの連携が可能であること トライアル期間を含め、技術サポートが手厚いこと
トライアル期間を含め、技術サポートが手厚いこと
新谷様:当初は、基幹システムのカスタマイズによって夜間バッチ機能を追加することを検討していました。しかし、柔軟性が十分でなく、機能面や費用面から導入は断念しました。
また、無料のRPAソフトも候補として検討しましたが、技術習得に対するサポートが期待できないことや、機能面での不安もあり、こちらも見送りました。最終的には、インターネットで「中小企業で実績の多いRPAソフト」を検索し、その中でRoboTANGOの存在を知りました。
当初は複数のRPAツールを比較検討する予定でしたが、トライアル期間中にRoboTANGOで当社が日次処理として実行したいと考えていた基幹システムの所要量計算(MRP)の処理を自動化できる見込みが立ちました。基幹システムのMRPを起動するだけでなく、当社のカレンダーをもとに稼働日のパラメーターを指定し、マクロと連携することでMRPを自動実行できると考え、実際に試してみました。結果的にこれがうまく機能し、そのままRoboTANGOの導入を決定しました。試行錯誤の過程で多くのアドバイスをいただけたことも、導入の後押しになりました。
一番の決め手は、画面操作の登録が容易だった点です。画像認識による操作がスムーズに行えたことに加え、他のソフトウェアやアプリケーションと連携できる点も大きな魅力でした。
田子様:RPAもRoboTANGOも初めて触れるものでしたので、操作が難しいと対応しきれないのではないかと考えていました。そのため、操作方法がわかりやすく、実際に使いやすかったことは非常に大きなポイントでした。トライアル期間があったことも良かったと思います。
新谷様:導入後のサポートも非常に手厚いと感じています。
例えば、導入当初にRoboTANGOがエラーで終了してしまうことがあったのですが、御社からエラー処理の方法についてアドバイスをいただき、それを組み込んだところ問題が解決しました。
また、キー画像がうまく認識できなかった際も、エレメント機能を使って実行することで正常に動作するようになりました。
さらに、ライセンス認証が月に1~2回できなくなることがありましたが、スターティアレイズさんに相談したところ、的確なアドバイスをいただき、対応後は問題が解消しました。
このようにサポート面でしっかり支援いただいたおかげで、現在は安定して稼働しており、大変助かっています。
所要量計算(MRP)や工程計画修正、受注データ取り込みなどにRPAを活用し、月間60時間の工数削減に成功
新谷様:現在は、所要量計算(MRP)・工程計画修正など計画関連業務や受注データの取り込みなど、さまざまな業務の自動化を行っています。
RPA導入前はMRPや工程計画修正などに毎朝2時間ほどかかっており、その間は他の業務に手をつけられない状態でした。
管理データは担当者へタイムリーに提供する必要があり、各プログラムを朝から順番に実行していました。
しかし、これらを順番に手作業で実行していたため他の業務に支障が出ており、データ提供も遅れてしまうことから、夜間実行への切り替えを検討していました。
RPA導入後は、今まで手作業で行っていた処理を朝5時にRPAで実行させており、出社時にはすべての処理が完了している状態になっています。
田子様:当社では、稼働カレンダーに基づいた基準日を自動で入力できるよう、専用のExcelマクロを作成しており、現在はそのマクロとMRP機能をRPAで連携しています。
これにより、工程計画が自動的に作成される仕組みが実現しました。
具体的には、まずRPAが社内カレンダーから基準日を取得するためのExcelマクロを起動し、そのマクロがカレンダー情報を取得します。
続いて、RPAロボットがその結果を受け取り、MRPに自動で入力します。
これにより、計画に対しての実績や受注情報が最新状態に更新され、毎日の工程計画が作成されます。
その後、工程計画修正マクロを実行するという流れです。
これまでは基準日を人が手入力しており、たとえば祝日であっても当社が稼働している場合は手作業で入力し直す必要がありましたが、RPAによって自動化が可能になりました。
新谷様:MRPと工程計画修正の処理が完了した後は、RPAが起動するExcelマクロにより結果データを集計・編集し、管理用データを作成しています。さらに、そのデータを担当者へ提供するまでの作業も自動化しています。現在は合計7つの業務で自動化を実施しています。
出社時にはすべての作業が完了している状態となり、IT担当者の作業工数を大幅に削減できました。結果として、月間約40時間の工数削減を実現しています。
これまで私や田子が出社後すぐに対応していた作業ですが、RPA導入により毎朝5時に自動実行されるようになり、人手作業が不要になりました。
IT担当者が他の業務に時間を充てられるようになったことは、非常に大きな成果だと感じています。
新谷様:管理部門の要望により、受注データの取り込み業務も自動化しましたが、この業務の自動化も非常に高い効果を上げています。
具体的には、顧客ごとのWEBアプリケーションからRPAが受注データを取得し、その内容をマクロが整形。その後、RPAが基幹システムに取り込むという流れです。
夜間に受注データを更新されるお客様が多いため、これもRPAで早朝5時に実行しています。
現在は数社分の対応ですが、それだけでも手作業が完全になくなり、月間20時間の工数削減に成功しました。今後は、すべてのお客様の受注データ取り込みを自動化していきたいと考えています。
RPAはリアルタイム性や工場全体の生産性向上にも貢献
新谷様:直接的な効果としては、月間約60時間の工数削減ができていますが、間接的な効果も非常に大きいと感じています。
例えば、加工現場での実績入力時の待ち時間がなくなり、「この時間は処理中なので入力できない」といった制約がなくなりました。その結果、見えない部分でも生産性が確実に向上しています。
また、進捗状況がリアルタイムに反映されるようになり、次工程への着手や出荷準備のタイミングも早まりました。工場全体の工程の流れがスムーズになり、リアルタイム性が大きく向上したと感じています。
川島様:RPA導入前は、現場や事務所では朝の時間帯に業務が滞留しており、処理が完了するまで待たなければならない状況がありました。
しかし、導入後は朝の時点でシステムが更新されているため、すぐに業務をスタートできるようになり、停滞していた時間が解消しました。全体の流れがスムーズになり、生産性向上につながったと実感しています。
今後は、さらにRoboTANGOを活用できる領域が広がることを期待しています。
田子様:以前は、上流工程が終わらないと次の作業に進めない事があり、朝のトラブル対応などで現場の作業が停滞することもありました。
RPAを導入したことで、朝からスムーズに業務が進められるようになり、大きな改善につながったと感じています。ガントチャートなど特定データのファイル保存忘れやヒューマンエラーのリスクもなくなり、ミスのないタイムリーな更新が可能になりました。
また、以前は「自分が休みの日に他の人へ依頼していた朝の業務」も、RPAが自動で実施するようになったことで、依頼や引き継ぎの手間も不要になりました。
新谷様:今後は、さらにロボット化できる業務を増やし、RPA活用をきっかけに業務そのものの改善も進めていきたいと考えています。
まだ自動化に対応できていない取引先の案件もあるため、できるだけ早く対応を進めたいですね。現在は、出荷実績入力の業務も自動化や、総務経理部門の業務についても、AI-OCRとの連携を活用して自動化を検討しています。
現在は主に田子が中心となって運用していますが、OJTで他のメンバーへの教育も進めており、今後はより幅広い業務で自動化を展開できると感じています。
RoboTANGOは中小企業やIT担当者にもおすすめ
川島様: やはり、定型業務が多い企業様には特に導入しやすいツールだと思います。
無料トライアルがあることや、サポートが充実している点も含めて、中小企業でも導入しやすい環境が整っていると感じます。
中小企業の中には、「IT化やDXを進めたいけれど、何から始めればいいかわからない」と悩まれている企業も多いと思います。
まずは、毎日ルーティンで行っている業務がどれくらいあるのかを洗い出し、「これが自動化できたらどうなるだろう」と考えるところから始めてみてはいかがでしょうか。
そうしたときに、一度RoboTANGOでの自動化を検討してみてほしいです。
新谷様:各部門での業務ロボット化も有効ですが、特に基幹システムに関わる業務がある場合は、RPAを活用すると良いと思います。
IT担当者のような専門知識を持つ立場から見ても、RPAを活用したロボット化は非常に有効だと感じています。
夜間バッチ処理という方法もありますが、基幹システムでそれを実現しようとすると、どうしても費用がかかったり柔軟性に欠けたりする部分があります。
その点、RPAはそうした課題を解消しやすく、非常に有用な手段だと思います。
田子様:RoboTANGOは、画像認識によるキー画像で操作できるため非常に汎用性が高く、使いやすい点が魅力ですね。また、サポート体制も手厚く、導入しやすいツールだと感じており、おすすめできるRPAだと感じています。
富士精機株式会社
https://fs-fujiseiki.jp/
製造業
76名(2025年10月現在)
RPA「RoboTANGO」
IT企画室
無